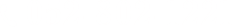概要
犬の甲状腺腫瘍は頚部にできる腫瘍としは一般的なものです。頭、頚部にできる腫瘍の約10-15%を占めます。腫瘍全体の発生率としては2%弱で高くありません。
犬の甲状腺癌腫瘍は90%が悪性で60%は両側性に発生すると言われています。診断時に約1/3の症例で転移が認められますが、転移した病変の進行はそこまで早くないと言われています。甲状腺腫瘍は大きく分けると濾胞腺癌と髄様癌に大別されます。
甲状腺癌は犬での発生が多く、浸潤性や転移性が高い腫瘍であることから注意深い観察が必要となります。また、多くが甲状腺ホルモン分泌機能を失った非機能性腫瘍であり、ホルモンを分泌能が高まり甲状腺機能亢進症を伴う機能性の腫瘍は10%程度です。一方で甲状腺細胞が破壊され甲状腺機能低下症を伴う事はあります。
好発犬種は、ビーグル、ゴールデンレトリーバーです。
甲状腺腫(良性)は臨床的に発見されることは稀です。他の病気の検査などで偶発的に発見されることあります。 その他甲状腺腫瘍に似たものとして、短頭種では慢性的な低酸素血症のため頚動脈小体腫瘍(良性)の発生がよく見られます。
猫の甲状腺腫瘤は組織学的に腺腫様過形成が多く、両側の甲状腺に影響がでます。 良性の腺腫が多く、悪性腺癌の発生は犬と比べて多くありません。
症状
頚部にしこり(腫瘤)が触れるようになります。 進行するにつれ、腫瘍が大きくなって周囲組織を圧迫するようになり症状が出てきます。よって喉や頸に影響が出てくるために様々な症状が見られます。
咳、呼吸が早くなる(呼吸困難)、ご飯を飲み込む時に不自然(嚥下困難)、鳴き方がおかしい(発声障害)、顔のむくみ(顔面浮腫→前大静脈症候群による)等。
診断
一般的な全身スクリーニング検査を行い転移の確認や全身状態を確認します。触診で可動性の確認や甲状腺ホルモン検査、細胞診検査を行って病態を調べます。超音波検査では通常豊富な血流が観察される。甲状腺癌は血流が非常に豊富になっているため、出血のリスクが高いためコア生検は避けるべきです。
X線検査では頚部の腫瘤は、筋肉との区別が困難なため、腫瘤辺縁を確認することが難しいことが多いため、気管が腫瘤によって変位していないかどうかを確認します。
両側性の発生や、正常な甲状腺の場所から離れた尾側で甲状腺癌が発生することがある(異所性甲状腺癌)ので、頚部全体の観察が必要です。
治療
外科的切除による摘出は根治的な治療となります。片側の甲状腺を摘出する場合、周囲組織への浸潤性が少なく、可動性がある場合、予後は良好でしょう。
一方で、腫瘍の大きさや浸潤の程度、甲状腺中毒の症状の有無、遠隔転移の有無、両側性の発生等の条件がある場合は、補助的化学療法や放射線療法との組み合わせた治療が必要になってきます。
術後の合併症としては、出血や喉頭麻痺、嚥下障害、ホーナー症候群などの神経徴候が認められることがあります。
両方の甲状腺を摘出した場合には、甲状腺ホルモンの不足が予想されるために、不足分の甲状腺ホルモン剤の投与が必要になります。また、甲状腺摘出の際に上皮小体(副甲状腺)も摘出しなければならない場合は、術後の血中カルシウム濃度の管理も必要となってきます。
放射線治療は甲状腺癌の切除が出来ない状況の場合に実施します。
化学療法に関しての効果はまだ報告が少なく不明瞭なところがあります。
腫瘍の切除が困難な場合、転移がみられる場合、あるいは転移が懸念される場合の術後の補助療法として犬で化学療法が効果を発揮する場合があります。
ドキソルビシン、シスプラチンで治療した犬の30-50%で部分寛解が得られた報告があります。そのほか、ミトキサントロンやアクチノマイシンDを用いた報告もあります。
分子標的薬の一つであるトラセニブ(チロシンキナーゼ阻害剤の一種)は犬の甲状腺癌で臨床的有効率として8割、その持続期間は25週という報告があります。